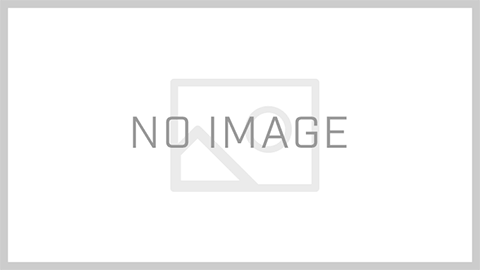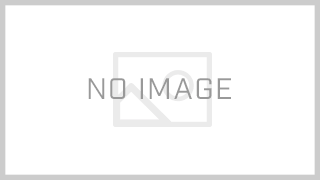娘たちの教育におけるグランドデザイン
皆様、こんにちは。キョンくんです。
長女が小学生になり、今後の子育てについて、グランドデザインを整理しました。あるべきがなければ、現状とのギャップが明確にできず、課題のあぶり出しもできないためです。当然ながら今後変わっていく点も出てくるとは思いますが、まずは現時点での最終到達点や戦略目標、戦術目標を整理しておきます。
最終到達目標点:
青春を楽しみ、社会性を学校で学びながら、学業に自ら打ち込める状態であること。結果、娘が望む進路を18歳時点で選べること。東京一科、医学部、早慶が狙える成績であること。
戦略目標:
謙虚な姿勢を持ちながらも、自己肯定感を高めた状態を維持し続ける。具体的には「昨日の自分を超えること」と「成績は単なる結果、されど結果」という意識付けを行う。
戦術目標:
小1時点で見えるところまでだが、5点挙げておく。
(1)学年の切り替えを負荷なく乗り越えられる先取り学習(特に英数)
(2)これまで行ってきた学習の連続性を意識したスモールステップ学習
(3)習慣化を意図した日々の学習トレーニング
(4)心技体の体を鍛える活動の励行(現状は自転車、縄跳び、スイミング)
(5)娘にも全国レベルを体験させる機会の提供
以下、上記の考え方となります。
最終到達点目標の考え方:
私の話から入るが、受験時代は青春だった。浪人の期間も含めて辛さは有ったが、楽しかった。在学中は部活動も最後まで打ち込めたし、文化祭や体育祭も本気でやれた。その青春は娘たちにも味わってほしい。ただ、私の反省としては世界を知らなさすぎた。地方出身で灘も筑駒も開成も桜蔭も知らなかった。その世界を知らなかったがゆえ、幸せを強欲に追求して大学受験も突っ走ったが、失敗して浪人した。知っていれば戦い方も変わったはずだと考えている。
娘たちには僕のように強欲に全てを得ようとしてほしいし、青春も受験も楽しんでほしい。よって、僕の失敗を学習して自分の力で昇華できている状態を観測できれば大成功だと思っている。
戦略目標の考え方:
常に学ぶ姿勢を忘れずにいれば、複利のごとく学習効果が目に見えて上がると考える。そのために必要なマインドが毎日の積み重ねを大事にする「昨日の自分を超える」ということと、高い自己肯定感である。自分はやればできるんだという気持ちを常に持たせるようにして、自己肯定感を誘発させる。
戦術目標の考え方:
(1)私の経験だが、中学入学時に数学でマイナスの概念がさっぱり掴めず、1年間を棒に振った。高校入学時には事前に配られた予習課題をこなしており、数学は問題なかったが、今度は英語でつまづき、大学入学まで英語の苦手意識が消えなかった。よって、特に学校の切り替わるタイミングに力点を置き、先取りを行っておく。もちろん学年の持ち上がり時も気を配るが、学校が切り替わるタイミングは競争環境の変化が如実に出るので、順位が大幅に変動する。深海魚リスクを避けるためにも事前の先取りを行う。私が住む地域は中学受験加熱地域ではないため、小6時点で最低でも中1の算数は少し触らせておく。英語は既に開始しているので、このまま伸ばしていけば問題ない。
(2)娘たちの幼児期学習はおはじきを楽しんだステージを通過後、もっぱらパパママとの口頭試問であった。算数で言えば1+1を頭で計算させ、難しければ手も使って、解いていく。そのように算数だけはやってきたのだが、結果として机に向かうのを面倒がるようになった。これに加えて文章題となると、自分で読まねばならず、更に嫌がる。よって、座らせる所から慣れさせ、文章題は一緒に読むようにした。これは効果が出たので、このように過去からの学びの延長線上となるような施策を常に娘との会話の中から浮き彫りにして実施していく。事実一緒に読むという着想を得たのも、娘の「パパが出す文章題だけが楽しい」という言葉を受けてだった。
(3)当たり前すぎるが、習慣化についても一言書いておきたい。現在幸運にも在宅での仕事ができる環境にあるため、娘はまずは夕方以降で国語算数で1ページずつは最低限学習する癖付けを行う。さらなる具体的手段は考え中だが、娘の目に付く形でモチベーションを上げる施策(日程表のようなもの)を考え中である。5月以降に実装を予定。結局習慣化なくして学力の向上はありえないので、ここは親の私も力を入れて作成したい。
(4)心技体は嘘だと思っている。事実は体技心である。体が丈夫でなければ、技術も心も鍛えることは不可能だ。よって、運動する時間は取ることを決めている。休日にはスイミングの習い事を入れ、自転車も既に十分乗れる状態にある。今後も定期的な遊びを通じて、心身の充実を図っていく。
(5)これは全国統一小学生テスト(通称全統小)を活用していくつもりだ。年長から始めたが、解けない問題も有るというのを実感してもらいつつ、できないことを悔しがり、親子一緒に考える時間を取るきっかけにしたいと思う。上には上がいるからこそ謙虚にもなれると思うので、日々の成長を褒めつつ、新たなハードルとさせていただくつもりだ。
以上